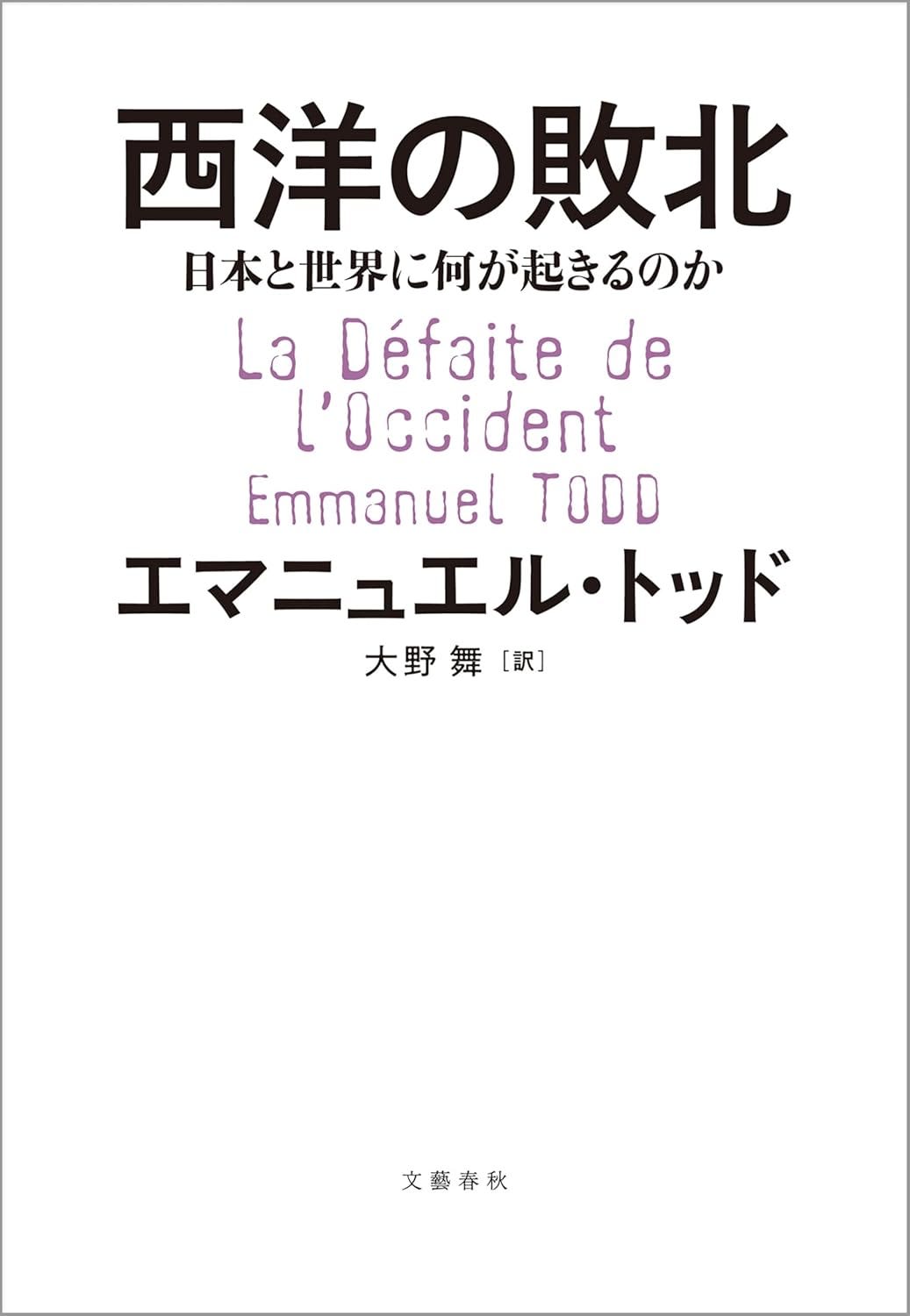#83 脱サイロで拓く 人文知のフロンティア with デサイロ 岡田弘太郎さん
~人文知と実践を繋ぐ~
今回は、人文・社会科学分野の研究者と協働するプロジェクトデザインファームである、一般社団法人デサイロの岡田さんをお招きし、組織の活動内容や現代社会における人文学の役割について話を伺いました。その文字起こしです。(ぜひ動画やPodcastで見ていただいたほうが空気感などわかるのでぜひ)
*宣伝:ANRI人文奨学金締め切り:2025年6月30日!ぜひ応募を!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYTN_M_hew_lrfARGUIPuyqtIekxpBLBkl0wr9dQJJMZ7Rw/viewform
中路: まずは簡単に自己紹介をお願いできればと思います。
岡田: デサイロの岡田と申します。主に今回の人文奨学金とも紐づくところで、人文・社会科学分野の研究者の皆さんと一緒にさまざまなプロジェクトを作っていくような、プロジェクトデザインファームを運営しております。
どういう存在なのかというのを言うのが難しくて。シンクタンクのような側面もあれば、財団のように助成をやることがあれば、戦略デザインファームのようなかたちでで学知を活用させていただいて企業向けにソリューションを提供したり。既存のさまざまなプレイヤーのさまざまな要素が入り混じった形式で運営しています。
中路: 普段だと「どこですか?どんな会社なんですか?」って聞くと、なんて説明するんですか?
岡田: 最近、悩んでます(笑)。最初はアカデミックインキュベーターと言っていたんですよね。特に人社系の研究者の方々に対するインキュベーションをやる団体ですと言ってたんですけど、必ずしもその側面だけではなくなってきてるので、今ちょっと悩んでます。
中路: 複雑なもの、何か言いづらいものだからこそ新しいことやられてるんだなと思う一方で、説明するのには難しいですよね。
立ち上げから2年半。人文学の視点からテクノロジーを捉える
中路: デサイロをやり始めて何年くらいなんですか?
岡田: 今、立ち上げてから2年半ぐらい経ちますね。
中路: 『WIRED』の編集者としても働かれてたんですよね。
岡田: そうですね。僕自身、兼業で実は『WIRED』日本版のエディターはしていたりするので、デジタルテクノロジーが社会や未来をどう変えていくのかはずっと自分の中でも関心テーマとしてあります。特にデサイロの場合はバーティカルに人社系の研究者の方々と取り組んでいく一つの団体として立ち上げたところですね。
中路: 『WIRED』って結構そのおもろい雑誌ですけど、テック寄りという、そっちの方向性から、今のデサイロもやり始めたキャリアとして、どういうベクトルで今人生を歩んでるのかな?
岡田: 『WIRED』にはデジタルテクノロジー、イノベーションといったイメージはもちろんあると思うんですけれども、そのなかでも倫理であったりとか哲学であったりとか、あるいはSFといったかたちで、テクノロジーをある種批評的に捉えたり、人文的な観点から見ていくことを実は長くやっていたりもするので、いわゆる理工系的な技術を起点としたイノベーションだけではなかった側面もありました。
なぜ今、人文学が重要なのか
中路: テクノロジーを批評的に捉えるのは、自分も2010年代とかにこのスタートアップシーンを含めて入ってきた、興味を持った世代なんですけど、あの時「テクノロジー最高」というか「テクノロジーが世界を変える」といったナラティブにみんな乗ってたのかなと思うんですけど、そういう批評文化って日本ってもともとあったんですかね?
岡田: 遡ると色々ある気がします。ised(情報社会の倫理と設計についての学際的研究)は、そまさしく2000年代の情報社会が立ち上がっていく中での、人文的な観点からの検討をされていましたよね。成田悠輔さんらも参加されてた東京財団の仮想制度研究所というこのがあり、そこに今のスマートニュースの会長をされている鈴木健さんも参加されたり。名だたる方々がそういった視点から検討された場が、実は日本にもかつてはあった気がします。
しかし僕の見立てとしては、昨今、LLMも含めてテクノロジーの進化が早すぎて、それに対してキャッチアップすることが、専門分野街の研究者の方も一般の方も難しくなるなかで、適切に哲学や倫理学の観点から捉えていくことが結構難しい時代になってるのかな、と感じます。
社会を捉えるスコープとしての人文・社会科学
中路: そのあたり含めて、デサイロを立ち上げた理由とか、そのあたりってどういう風な経緯で立ち上げていったんですか?
岡田: こういう活動をされている方々って、もともと研究者を目指されてたとか、ご両親が研究者でそういう研究者を取り巻く環境がうまくいっていないので、それを変えたいというところで、アカデミア支援型のスタートアップや新しい団体を立ち上げられることが多いと思います。僕自身はそういうバックグラウンドあんまりなくって、編集者なので、未来がどうなっていくのか、今の時代の欲望は何なのかを考えるのがすごく楽しいというか好きというところがありまして。
その中で、人文的な観点から見ていった時に、今の時代の社会状況とかあり方がすごくいろんな見え方がしてくるので、種社会変化とか、そこのインサイトを見ていく一つのスコープとして人文社会科学の知見に興味持っていった部分があります。
なので、ビジネス的な観点でいうと、企業の方にそういうインサイトを提供していくとか、そういった活動をデサイロでやっています。ただ、それ自体が研究者の方々を取り巻く環境を変えていくことにつながらないかっていうと、結果としてその環境改善につながることを目指したいと思っています。
脱サイロ化の必要性
中路: デサイロ、つまりは脱サイロ化を意味すると思うんですけど、そこにはどんな意味が込められているんですか。
岡田: もともと人類学を学ばれてて、『ファイナンシャル・タイムズ』の編集長をされていた方の『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』という本があります。その中では、高度に発達した社会が、基本的にはどんどん専門文化していくという議論が行われていて。学問分野も同じで、例えば学問分野が違うと同じ言葉を使っていてもその定義が違ったりっていうことがあったりする中で、どんどん細分化・専門分化が基本的に起きていく中で、ただ一方で社会の課題に応えていこうとすると、基本的にはさまざまな知見を組み合わせて総合的にアプローチしないと、世の中の課題は解けないと思います。
そうした意味もありますし、学問と社会をブリッジしていくことをしていきたいので、脱サイロという意味でのデサイロと名付けました。
プロジェクトを通じた異分野交流
中路: どういう取り組みをしたらもっと脱サイロ化していくんですかね?
岡田: すごく難しくて、我々がやったケースで良かったのが、昨年、DE-SILO EXPERIMENTというプロジェクトをやりまして。研究者の方にまず研究テーマを定めていただいて、それが今の時代と社会に応答するようなテーマを決めていただいて、前半のパートではその研究について進めていただくんですね。後半のパートではアーティストの方にコラボレーターとして入っていただいて、それを作品やパフォーマンスにするプロジェクトを昨年やりました。
その研究者の方とアーティストの方って全く異なるフィールドにいらっしゃるっていうところはあるんですけれども、実は背景に持っている同時代的な課題意識が共通していたりとか、プロジェクト化することによって越境してコラボレーションできるところがあったりしていて。
そういうプロジェクトを作って、いろんな方が交わる機会を作ることですとか、空間や場所を少しずつオーガナイズしていくことでしか進んでいかないのかなと思ったりしますよね。
コミュニティは作れるのか?:オンラインとオフラインの課題
中路: オンラインってやっぱりそれはできづらいんですかね?この脱サイロ効果みたいな。
岡田: そうですよね。自分が観測できてないだけな気もするんですけど、同質的な集まりは色々うまくいってる気もするんですけど、オンラインで本当に異質なもの同士がぶつかったり衝突し、よい意味での創発が起きることが、今のインターネットとかオンライン空間で生まれてるかっていうと、あんまり事例がわからないなと思ったんですけど。
中路: ゲームとかDiscordがどういうコミュニティが盛り上がってるのかを見ると面白いのかなと思ったりしていて。XとかTwitterって広すぎてエコーチャンバーで見えるものが見えていくみたいな話になっていて、興味あるけど、端と端みたいなでもベン図では微かにつながっているっていうのを組み合わせるのにインターネットっていうのは相性が悪いのかなとか思ったりしていて。
ANRIの人文奨学金について
中路: 今回人文奨学金を発表させていただいて、自分も以前から人文知には興味はあったんですけど、年々そのあたりのテーマ感がホットになってきてるというか、大事だよなという感覚が5年前とかとかと比較すると、より強い意識はあって。ANRI人文奨学金のこと含めて、その辺りどのように意見を持ってますか?
岡田: リリースを見させてもらったときには端的に素晴らしいなと思って。基本的に僕らの考えも、それまでアカデミアや研究者に流れていなかったお金が流れていくってことがすごいポジティブで重要だなと思っています。
今の資本主義の仕組みや構造、ルールの中で、突然大きく生まれるお金はやっぱり局所的にあるわけじゃないですか。
そのお金が生まれる仕組み自体がすごい発明だと思うんですけど、生まれたお金を何に使うと世の中が面白くなるのかとか、人々の自由とか創造性のためにそのお金が流れていくのかみたいなことを常日頃から僕もずっと考えてるんですけど、その中でやっぱりANRIさんの人文奨学金の取り組みはまさしくそういうプロジェクトであり、お金だなとすごく思ったので、素晴らしいなと思っています。
長期主義とナラティブの重要性
中路: 僕らはお金を預かって増やす仕事ではあるものの、短期主義でもなく、ベンチャーキャピタルとかエクイティファンドのいいところというか、時間軸を長く見れるみたいなのがいいところだなと思ってます。
10年でお金を一旦増やして返すという仕事なのでもちろん短いといえば短いんですけど、ただ1年で何かが変わるというわけでもない期待値で僕らも活動しているというところは、このマインドセットってすごく大事なのかもなみたいなのは7、8年働きながら思っていることで。
今の投資とか今の活動が10年、20年先とかに目吹くじゃないけど社会が1個変わる可能性があると思いながら、ただ1、2年では何も変わらないかもしれないみたいな、そういう期待値で動かざるを得ないマインドセットになっていくなと思っていて。
岡田: いつも中路さんがおっしゃられてるやっぱ新しいナラティブを作ることもそこは通じてくる部分ですよね、きっとスタートアップとしても。
中路: 固定化していくナラティブだと面白くないなと思うし、より変化を生むためにはテクノロジーだけでなく、どういう物語を作って、どういうセンスメイキングというか納得性みたいなところは重要になってくるだろうなみたいなところは、なんとなく自分の中でも思ってます。
海外の著名なVCとかがどっかの記事で読んでいた時に「ナラティブを作ることが仕事です」みたいな話もどっかで書いてあって、なるほどなみたいな、そういう捉え方もできるんだみたいなことを感じて。
人文奨学金で求める人材像
岡田: 人文奨学金で、どんな方に応募いただきたいとか、どんな方と出会いたいみたいなところってあったりするんですか?
中路: 基本的な学問に優劣付けたくなかったので、幅広く人文系といっても本当に人文いわゆる人文学だけじゃなく人文社会科学含めてその定義は広く取りたいなと思ったんですけど、どうせベンチャーキャピタルがやるならという意味において、その未来とか社会っていう意識みたいなところは考えている方とお話したいし、そういった方に対して奨学金を給付したいなと思っていたので。
質問とかで、自分がやっている研究を聞いているのは、他と同様に聞いているんですけど、その研究が、ちゃんと進んでいったりとかやれると未来や社会とかがどう変わると思いますか、みたいなことの質問を入れたのは、そこの意図が強くて。
そういった社会や未来を、もちろん研究に没頭することが大事な一方で、何かどこかでそういった接点みたいなところを考えていただける方と、ベンチャーキャピタルとしては結びつきたいというか支援したいな と思いがあって、そういった人たちと出会えれば嬉しいなと思ったりします。
最後に
中路: 締め切りが2025年の6月30日なので、もしこれを見ていただける方がいたら申し込んでいただければなと思いますし、友人に勧めていただければなと思いますし、デサイロの方々とかももしお知り合いにいたらちょっと言っていただけたら嬉しいなと思っております。
また是非、その辺の採択者とかも、こういうビデオポッドキャストとか撮ろうかなと思って、どういう研究してるのかと知りたいし、それをこういう風な形に残していくことが、長い、だらだら喋る力みたいなことも重要なのかなと思っていて。
これを観やすいようなコンテンツにしようと思うと、若干やっぱりその同質性なものしか集まらない気もしていて、なんかこういうポッドキャスト、ビデオとかテキストじゃないけど、YouTube番組でもないみたいな、そういうところに次の影響可能性とかのコンテンツがあるんじゃないかなと思って。
岡田: そうですよね。結局読まれる、見られる、ビューを稼ぐっていうと、やっぱり最適化される切り口とかネタに収斂されていきますもんね。それを期待せず、幅広く見てくれてたら、雑談の延長ぐらいで見ると気づくこともあるかなと思っていて。
中路: テクニック力の時代じゃなくて雑談力の時代でもあるのかなと思いながら見てる。最近考えてるっていう感じで。どうやるというかこうでこうで人文を支援する理由はこれですみたいな感じでプレゼン作ってやる時代でもないですし、僕が考えてるのはそういう話でもないので、こういうダラッとした議 論を、誰かの方が僕らが知らない誰かが聞いてくれてて興味をいずれ持ってくれてて みたいなところっていうのが、そのコンテンツをずっと貯めていくと何かあるのかないのかみたいなことを、ちょっと試したいなみたいなとは思ってます。
この辺り今のアメリカ・イラクなどを見ていも感じることがより明瞭に書かれてあった。ある種の暴露本のようにも思える内容だが、この今の時代を考えると理解できうる。
西洋はもう自明の中心じゃない、という宣告だった。ウクライナ戦争も制裁も、米欧の“崩れかけた家”から吹き出したひびのように映った。プロテスタンティズム・ゼロ――勤勉と公共心を支えていた見えないOSが停止し、空洞化した社会回路にポピュリズムやアイデンティティ闘争がうごめく。西側が掲げてきた「自由と秩序」の旗は、実は内部の粘性でしか保てていなかったのだと気づかされた。日本は長く、その旗の下で風向きを見ていればよかった。だが旗自体が裂け始めた今、どこに羅針盤を置くかを、自分たちで決めなくてはならない。