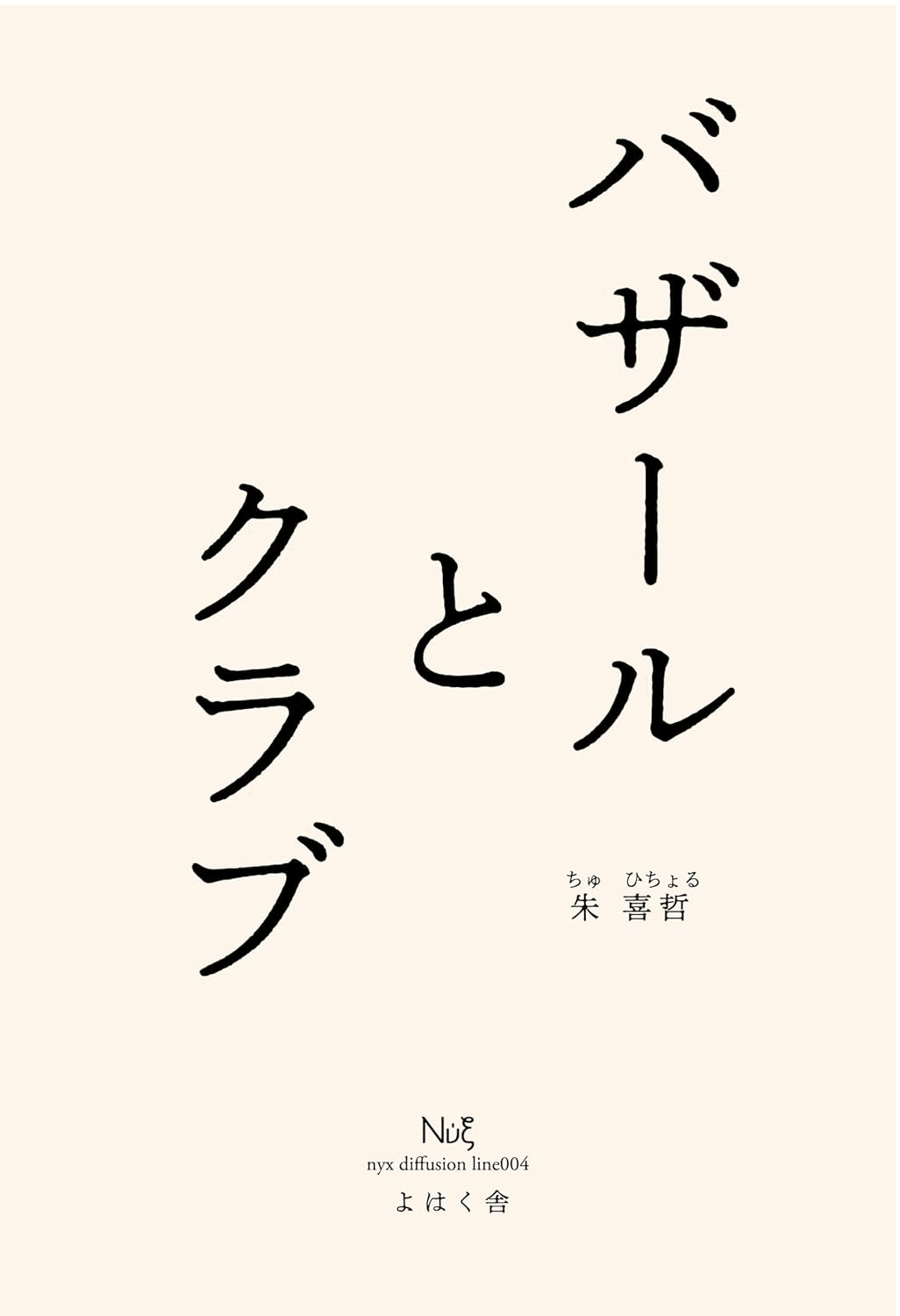#91 バザールとクラブ = XとPodcast
私的なクラブとしてのPodcast文化
最近Podcastなどを始める人がこの数年で増えていっている気がする。このPodcastの現象は数年前のPodcast来るかもというモメンタムと違う領域から来ている気がしている。それがローティーの言うバザールとクラブという概念で表せるような気がして、書き始めている。
ある種今回は朱 喜哲さんのバザールとクラブの書評でもあるかもしれない、この本を読みながら感じたことを書いてみる。ぜひ面白いので読んでほしい。
AirpodsのPF変化とともに伸びると思ったPodcast
これは自分の仮説ではあったが、VCやスタートアップ業界としても5-6年前以上にPodcastというのは一つ投資テーマであり着目トレンドではあったように思える。個人的にはそこにはApple の airpodsの登場に着目していた。あの発明により、人々がより耳を使うようになるのでその時にPodcastというフォーマットもより伸びてくるのではないかと思えた。
その先行市場となるUSではPodcastマーケットが非常に伸びており、それに倣った形でもある。ただそこまで急激には大きくならなかった。これは良く言われる話だが、USと違って車で聞くものとしてPodcastが最適なのだが、特に日本の東京においては車の需要が少ない。自分も車に乗って思ったのだが、やはり運転時の耳は空いている(書きながら思ったが、地方の人たちはほとんど運転しているはずなので、まだ空いている?それでもUSに比べると国土の大きさが違うから運転する平均時間が違うのかもしれない)
X/TwitterへのカウンターとしてのPodcast
このところのPodcastはどうやらそういったairpodsの変化とか、Sporitfyなどへのプラットフォームシフト!みたいな影響だけではない中でのトレンドのような気がしている。自分が雑誌を作った理由でもあるが、既存のSNSと言われているようなX/Twitterに対してのアンチテーゼ、カウンターとしての需要が伸びて来ているように感じている。そのカウンター感へのアナロジーとして、バザールとクラブを引用したい。
バザールとクラブ
この概念に出会ったのは、100分de名著偶然性・連帯・アイロニーを読んだ時で、その時から面白い概念だなと思っていたけれども改めて今回バザールとクラブというその部分を中心とした概念を読んで、理解が深まった。
簡単にいうとパブリックな空間をバザールと定義し、私的な空間としてクラブを例として捉えている。バザールは誰にでも開かれているが、その分自分と価値観が合わない人とも出会う。クラブはその逆で自分の安らぐ場所となりえる。この辺りの説明は下記引用を読んでいただくほうがわかりやすいのでぜひ。
バザールにいる限り、どのような人とでも接触する可能性はあるし、お店を営む側の目線で言えば、「嫌だな」と思うお客さんもいる。しかし、それでも商品を売るためには、愛想笑いを浮かべながら、うまく接客してモノを買ってもらう必要があるわけですよね。
つまり、バザールにいる限りはどのような人とでも交わる可能性があり、生活のためにはどのような人とでもうまくやりながら、必死に働く必要がある。バザールはすべての人にとって必要な空間であると同時に、そこにいるだけで疲れてしまう場所でもあるわけです。
(中略)
だからこそ、そんなバザールから家に帰る途中に立ち寄って、ほっと一息つけるプライベートな空間が必要です。
ローティはそのような空間のことを「クラブ」と呼びました。クラブに行けばバザールの愚痴を言えるかもしれないし、顔見知りたちと他愛ない話をしながら、バザールでの疲れを癒やし、翌日にまたバザールに向かうための英気を養う。
ここでのポイントは、バザールが唯一のものであるのに対し、クラブは無数に存在し得ることです。つまり、すべての人がそれぞれの「自分の場所」を持つ必要がある。ローティは、世界には「一つのバザール」と「無数のクラブ」が必要だと言っているわけです。(「暗がり」が失われたこの世界で、嗜好品は“われわれ”を生み出す:哲学者・朱喜哲)
バザールとしてのX、クラブとしてのPodcast
この表現から当たり前だが、今のXはバザールとなっているのではないかと思う。例えばこれは昔のインターネットコミュニティがハンドルネーム文化など含めて、現実のオルタナでありどちらかというとクラブ的なノリであったと思う。たかがネットの意見の時代だ。
しかしこれだけ普及した今においては、一大バザールとなっている。そのバザールには気の合わない人もいるし、ある種のバザールにおける手続的な正義というのもできてきていると思う。この正義というのはポリティカルコレクトネスにも近い気はしている。その正義の感覚がバザール全体を覆っている。この感覚がないままに発言したりすることで炎上してしまう。
しかしそういった気を遣ってばかり発信していくことは人間も疲れる。そういった意味において居場所としてのクラブがインターネット上にも求められるようになって来たのではないか、それはdiscordのような場所にもあるのだろうが、公共性を持ったクラブ(半開きのドア)みたいな感覚においてPodcastというものが選ばれているような気がしている。
音声は親密さを醸し出す
音声というものは不思議なメディアだ。映像メディアとしてのYouTubeの方がもちろん情報量が多いのだが、音声だけの方がIntimacy・親密さを感じる気がしている。普段自分たちも人と会話する時、ずっとその人の顔を見るのだろうか?と考えたらそんなことはない。話をするときは、その人の顔を見ずに他のところに目線をやったり、風景を見ながら話したりすることも多い。特にビジネスシーンではなく、親密な友人などとはそうなりがちな気がしている。なので音声のみの方がそういった気持ちにさせるのかもしれない。
ただクラブには危うさが非常にある。内輪ノリだしバザールで気にしていたような正義さというものを逸脱して発言してしまうことがある。それは仲間内だからこその話にはできるが、それをPodcastでやってしまうと全世界にある種放送されてしまう。そういった意味で半ドア空いているようなクラブな気がしている。
しかしそういう文脈においても音声というのはちょうどいいのかもしれない。ラジオとかになると流石に多くの人が聞いているので炎上したことは見たことあるが、それ以外においては映像やテキストに比べては炎上しづらさもあるのではないかと思う。検索しても即座に切り抜き文脈が拡散されにくく、音声の長さが誤読のコストを押し上げる。声質や躊躇、ため息が文脈を補完し、攻撃性を緩和したりする。テキストだけ、もっというと140文字の制限の中のXよりははるかに炎上はしずらい。
そういった意味においてローティがいう無数のクラブというものは、無数のPodcastという形で世の中に浸透していくのかもしれない。番組的というよりは、行きつけのバーでよく見る人たちの会話を盗み聞きするような感じで親密さと緩やかな排他的な空間として。
そういったものが以前かいたように共同体への回帰的な現象としても起こりうるのではないかと思っている。そのさらに先の文脈としてオフラインイベントなども多くもしかしたら今後流行るのかもしれない。より強固なクラブの組成のために。
リアリズムなリベラリスト=ローティ
ローティの考え方で面白いなと思うのが、すごくリアリズム的というか理想に終わらないような考え方で論を展開していることに思える。例えば理想だけをいうとバザールというのはポリティカルコレクトネスを考える場所であり、それに適した行動を全員が取るべきだという論もあると思う。
一方でローティは人間はそういうものではないという話をしているように思える。誰だってムカつくやつは出てくるし、バザールのことだけを考えて発言や行動をずっとし続けるのは難しいのではないかと考えているように思う。そもそもその何が正しいかというのも非常に曖昧であるし、そこに対しても問いを立てることを彼は大事にしている。
今回読んだ本の中にも、エスノセントリズム(自分が属する文化・集団の価値や規範を“標準”だとみなし、それを基準に他文化を評価してしまう心性/傾向)についての考え方が非常に自分的には面白かった。自民族中心主義という翻訳ができると思うが、読んで字のことくぱっと見は悪いものに思える。排外主義にもつながるし、一方で今の時勢を残念ながら反映もしているようにも思える。
一方でローティーはこのエスノセントリズムに対しても重要だという話を展開している。その観点が面白いし、ボッキャブラリーということを重要視する彼らしさがある。
ざっくり自分の理解を話すと、何が正しいかとかの価値観を考え出すと、袋小路に陥ってしまう。なのでエスノセントリズムという概念からは人間からは逃れられないし、むしろそこに立脚していることを自覚的になる必要がある。だからこそ"クラブ"という存在が人間にとって重要なピースになり得るということが書かれている。
自分たちの奉じる普遍主義的な価値観が文化負荷的であることに鈍感で、厚顔無恥でさえある文化的帝国主義者という醜悪な自画像がある。
他方では、普遍的諸価値の文化負荷性に敏感すぎるあまり、相対的には正しいが両立しない諸価値の狭間で身動きがとれなくなり、何でもありの思考停止に陥るか、あるいは冷笑的になってしまうという袋小路があるのだ。(バザールとクラブ)
「エスノセントリズム」はリベラルな民主主義社会に限らず、あらゆる社会において、その集団に「道徳的効力」がはたらくためには、むしろ不可処なのである。(中略)
「エスノセントリズム」とは、わたしたち何らかの文化に生まれ、そのなかで育たざるをえない人間にとっては、どうしても完全に無縁ではいられないものである。それは、過剰でも過少でも危険なものであり、いつも乗りこなすバランスが問われる、わたしたちの思考の傾向性なのだ。(バザールとクラブ)
わたしたちリベラルがすべきことは、異なる個々人や諸文化が、お互いのプライバシーを侵害することなく、またお互いの善の構想に干渉することなく、それでもいっしょにやっていくことを可能にするという、リベラルな諸制度の実践的な利点を挙げていくことだけなのだ。
(中略)
私的なクラブがもつ排他性こそが、ひとつの理想的な世界秩序においてきわめて重要な機能であるかもしれない(バザールとクラブ)
こうした考え方は非常にリアリズムな考え方であると思うし、自分は賛同できることが多い。今のバザールなインターネットにおいては、発言一つをすごく気にしながら行うしかないし、それはある程度仕方がないことになっていると思う。むしろそのルール感というのは大事な気がしている。
一方でそれだけだと窮屈であるし、本当に伝えたかったことは書けなくなってしまう。そういう意味においてクラブの必要性がより生じてくる。エスノセントリズムを保つクラブと、ポリティカルコレクトネス的な普遍的原則の中でのバザールどちらもが重要だ。
そうして複雑な社会を複雑さを寛容したまま捉えていきたいし、仕事としてはそういったクラブ的な起業アイデアはこれから注目しているし、まだ伸びていくのだろうと思う。
愛と正義が統合した究極的な政治形態とは、私的なナルシシズムと公的なプラグマティズムの複雑に絡み合ったコラージュであることが判明するかもしれない(バザールとクラブ)
Podcast:
#34 いつからiPhoneに期待しなくなった?均質化の時代と“欲望”の行方(ゲスト:kern タカヤ・オオタ)
デザイナーのタカヤさんと、iphone17の話をしながら、今の欲望ってなんだろうなという話をしております。ぜひ聞いてみてください。昔の家電とかワクワクしましたよね、、
#35 「人文知」:奨学金第一期生、10名の研究をざっくり紹介
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000040191.html
やってきた人文の奨学金の第1期の方々について自分の方でざっくり紹介していくPodcastとなります。全部の研究面白いのでぜひ見て、聞いてくれると嬉しいです。採択させていただいた方々もPodcastに出る・・かも・・?
本の惑星にも読んでいただいた内沼さんの本を読み返した。読んだのは2-3年前ぐらいになるから、今読んだら改めて感じることも多かった。本屋という空間の可能性はまだまだ正直あると思っている。しかしどういう本屋がいいのかは自分も思い付いてはいないが、本を売るわけではないが本がある空間の良さというのはまだまだ表現しがいがあるのではないかとも思っている。
この中にも多くのヒントはあった特にB&Bにおいてのイベント運営などは非常に参考になることが多かった。自分もいつか本屋はやってみたい。
「本屋」は「空間」ではなく「人」であり「媒介者」のことである。それはたとえば、必ずしもリアルの「書店」を構えていなくても、「本屋」であるという「あり方」が可能であるということです。