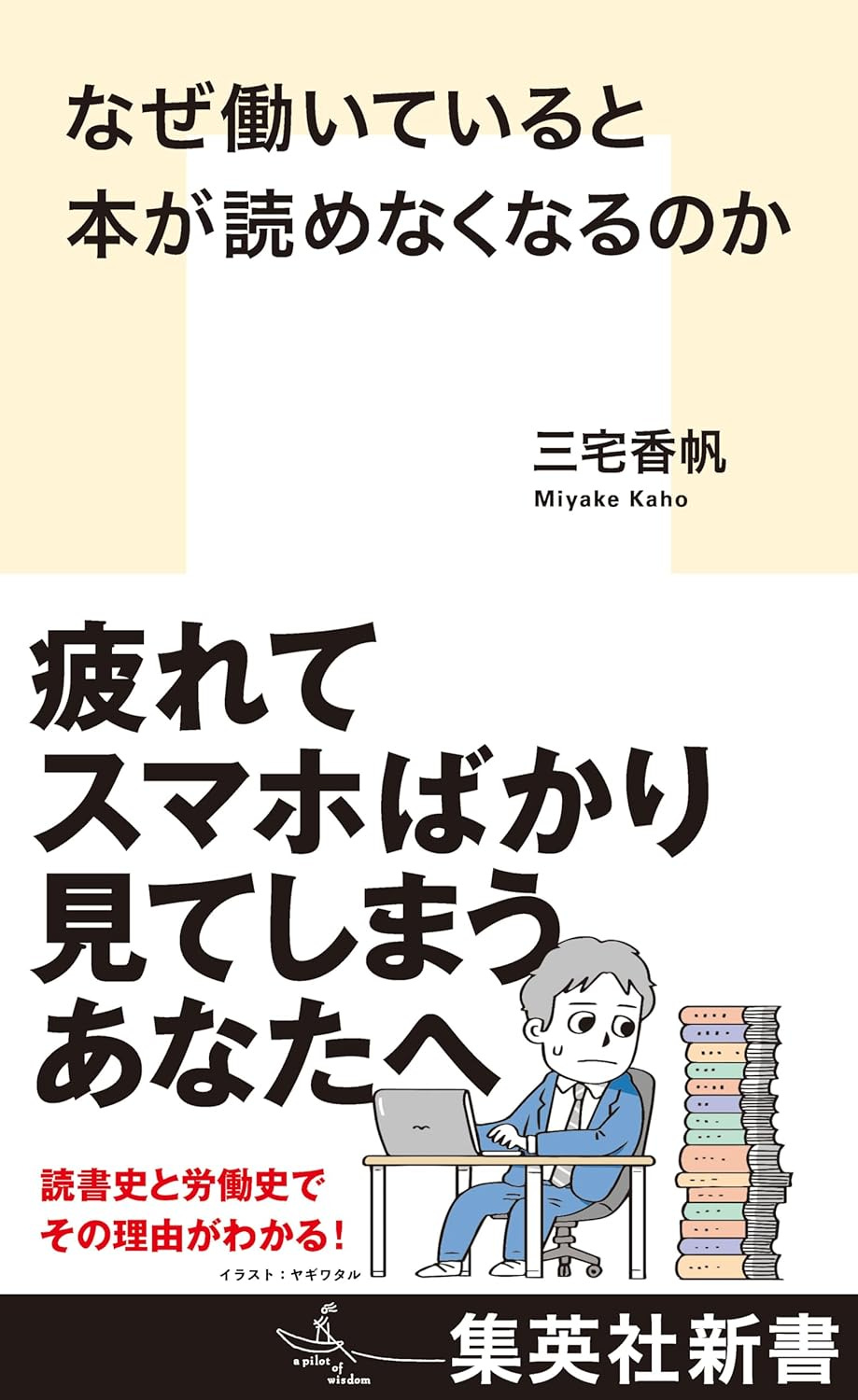#68 2024年冒頭の投資テーマ仮説振り返り
AIに着目してたが投資はあまりできなかった
あっという間に1年が経ってしまう。早すぎる。今年何ができたのだろうかと自分を振り返る間もなく、12月も過ぎていくはず、、そんな中でも一応毎年続けている今年の冒頭の投資注目テーマに対しての振り返りを簡易に行いたい。
今年は投資が少なかった
今年はまずは自分の新規投資でいうと3-4社ほど(見込み含めて)というようになりそう。追加投資のほうがやはり圧倒的に多い1年となった。その中でも公表した投資先は灯白社のみかなと。
全体感みると2022-2023はクリプトへの期待、2023-2024年はAIへの期待みたいなのが込められているが、まあズレは今後もあるのだろうなと思えた。
こちらが今年の1月9日に書いた2024年の投資テーマ仮説について。この記載をもとに、今年を振り返って実際に投資できたかどうか、そういう現象が起きたかどうかについて考えてみたい。
#39 Requests for Startups 2024
毎年1月にその年にどういう投資領域が注目されるのだろうかということを書いているのだけれども、それもマンネリ化してきたなと思うと同時にふわっと領域っぽく書いても、あんまりおもしろくないなと思いました。
①減速すべき分野への投資:政府や補助金と上手く付き合って産業を立ち上げられないか(△)
あんまり本格的には探せなかったなというのが正直なところ。一方で今年自分のなかでBig issueという言葉をつかってこのあたりのテーマはVCが扱えるテーマになってきたことを書いてきた。
VCのファンドサイズが大きくなることによって解けるIssueが拡張してき、例えばDefenesetechやClimatetechなどのようなスタートアップ単体でコントロールできるものというよりは、国家などの力をレバレッジしながらそういったBig issueに挑むスタートアップというのは増える可能性はある。
そのようなBig issueの投資というものは来年も続くトレンドにはなりそうな気配はあるが、一方でスタートアップの立ち上げ型のイメージはまだつきずらい。一社未公表だが新規投資をしたところもあり、このあたりのBig issue系のテーマは今年投資をした。(まあ厳密にはそこまでのBig issueではないが、人材不足系)
そういった減速させるべき分野については、例えば気候変動における、グリーンプレミアムのように費用がなにもしないと安いほうに流れるため、そこを補助金含めてインセンティブ構造を変更させる必要がある。そのような流れを創っていくことができるようなスタートアップを探している。補助金などを活用して上手く産業を立ち上げられるような分野というと非常にスコープが広いが、そういった戦い方をしていくスタートにシード投資をしていくことは意味があるように思える。
②会話形インターフェースで既存ソフトウェアを再構築できないか(△)
AIによって今年なにかこのあたりのインターフェースはテキストでチャット型・会話型で行われることは体感増えた人もいるのではないだろうか、AIに敬語を使う派と使わない派などいるかもしれないが(基本自分は急いでいない限り敬語派)、会話型のインターフェースはよりおおくなる可能性はある。
いま自分たちが普段つかっているソフトウェアがより会話型になっていく可能性は高い。かといって今年でそういったサービスが普及したかというと周りをみているとそうでもない。なのでこのあたりにまだ可能性が残っているのではないかとは思う。デザインの領域など含めて会話型のインターフェースでソフトウェアが再発明されていくことを期待している。投資はまだしてない。
生成系AIによって会話形インターフェースがより普及していく可能性がある。2024でどこまでいけるかは正直わからないが、この延長にARグラスの世界もあると思っている。GUI・マウスで操作しクリックしてなにかを動かすソフトウェアはダサいよねって20年後ぐらいには言われる可能性がある(わからないけど)
③AIによる学習方法/体験の再構築できないか(△)
SpeakAIなどが大型資金調達などをしているが、AIと学習みたいなテーマは投資をしたかったが、まだできてはいない。AIの活用方法として学習の最適化とかはもっと教育現場では昔から機械学習などであったことかもしれないが、更に学習体験や効率化を図れるものはできるのでは?とは思っている
AI-scratchedな学習塾や、料理を覚えるのにAI使ってなにかできやすくなるとかそういったものは増えてきそうな気がするような、しないような。。
生成AIの実装により、問題が動的に作れたり、よりコミュニケーションを促したりすることが可能になるはずなので、例えばシュリーマンの例ではないが、今のお金持ち達がどのように新しいことを学んでいるかというものを低コスト(人を雇わずに)に実現ができるようになるのではないか。そういった学習体験の再構築ができるようなものに対して、投資をしてみたい気持ちはある。
④New Brandの作り方を教えてほしい/モノの記号化の加速(△)
AIの登場によって生成コストがより様々な場所で低下していくとしたら、なにがほしいかどれを選ぶかにおいては記号的な要素がより強くなっていくような気がしている。コロナのときにLVMHの収益が伸びていき、時価総額が最高を迎えたようにブランドという言葉含めてそういったものが強くなっていく気がしている
D2C的経営みたいなことも今年記事では書いたが、企業自体のブランドやそういった見せ方も今後工夫が求められるはずだ。初めてVideo podcastを前回とってみたが、ああいうようにVlogっぽさの表現含めてその企業を示すあり方は変わってくるはずだ。
そういった新しくブランド・記号の普及を加速させていく方法や加速させていく志をもった企業に投資をしてみたいが、今年はこのテーマにおいての新規投資はできなかった気がしている。
使い古された話ではあるが、ボードリヤールが消費を単なる物質的な行為ではなく、記号やメッセージを通じた社会的なコミュニケーションだと定義している。その記号化ということが加速している印象がある。ブランドをつくるということは記号自体をどのようにつくっていくことができるかということがキーになる。その時代におけるメディアが重要だと思うが、そこも多様化していく現代においてどのように記号・Brandをつくっていくのか興味がある。
⑤流通の新しいパッケージ発明とはなにか(△)
どういう商品をつくって、どのような商流・売り方で売るかみたいなのはどんなビジネスにおいても重要な観点だが、そのどういう商流・流通にするのかについてはもう少し発明があってもいいように思える。
例えばランダム販売や、オリパみたいなのはガチャガチャのようなものに近い楽しさもあってお金を払っている。GENDAなどが進めているゲームセンターを流通として捉えていてUFOキャッチャーなどで推しのキャラクターと出会えるみたいなもので流通の場として捉え直したIR資料など(詳しくは暇と退屈のプライズゲームをぜひ)を見ていると思えた。
自分の投資先だとTicketMeとかは近いのかもしれないが、今年このあたりに投資はできなかった。
そういった中で、今後はその流通で買う理由の発明などがより増えてくると面白いと考えている。例えば、償還可能なNFTみたいなものは流通の発明になりうるかもしれない。その他にもランダム性に対してのガチャガチャなども一つ発明ではあるだろう。抽象的だが、今非常に流行っているトレカなどもこのテーマに内包されるかもしれない。
⑥家の再発明をどうできるか/Teslaの家版とかどうでしょ(✕)
このテーマは自分もすごい気になっているが、結局は投資はできなかった。でも家へ求める期待は今後も変わり続けるはずで、このあたりは投資はしたいなと未だに思えている。
ANRIの投資先のNOTAHOTELにはじめて今年伺えたが、感嘆するプロダクトであった。いろんな周りのガジェットはこの10年の間で変わったり進化してきたけど、家の進化はそれに追いついていない。家をプロダクトとして捉えてもう少しみんなが住みたくなるようなものは今後も考えたいし投資をしたい。
家の役割の変化一方で家への関心度は年々高まってきている。それは例えばコロナをきっかけとなり、リモートワークなど働き方の多様化が社会に認められるようになり、家という存在が単純に寝に帰る&土日を過ごす少し無機的な存在から、働き・交流も行われるような有機的な存在へと期待値が高まっているように思える。しかしそのニーズに答える発明がまだ少ない気がしている。
⑦個社最適のSaaSを作るための何か/SIer Update?(○)
このあたりは皆話していることではあるが、SaaSのような汎用性で解ける課題と、個社の改題みたいなのが交わるポイントは今後も増えてくる気がする。投資先のdiniiがAll in one SaaSのようなことのようにプロダクトを複数だしてその交わるポイントをすべて解いていこうとしたり、もしくはSIerのように1社にフォーカスして組み上げていくようなこともあるだろう。まだまだこのあたりは今後も伸びそうではある。
Composableで、Interoperability (相互運用性)あるようなシステム設計ができるようなものが増えてくるはず。基幹システムを基盤としたComposableなシステム開発が求められるようになるはず。 この延長にSaaS同士のM&Aなどはもっと増えて叱るべきだと思うし、Compoundというように複利が効くように、プロダクトを複層化していく流れは続くと思う。
⑧微かな領土性を感じるものは人類には必要 /コミュニティ再興/ Closed SNS?(△)
より悪い意味で更にこの分断が進んだ年であったなとは思う。リベラルさについて前々回書いたように、このような課題は深刻だと思う。
そういった領土性のために新しいSNSなのか現実世界のコミュニティなのかそういったのを取り戻せるものに投資をしたかったが、今年はできなかった。ただ今年後半からスポーツなどに積極的に行くようになり、そういったものにかすかな領土性を自分は感じた。より今後はスポーツのようなものが生活に必要になってくるのではないかと思ったりもする。このテーマでの具体的なアイデアはスタートアップ的なものなかはわからないが、自分でも来年も探していきたい。
その拠り所は昔は家族であったり、地域のExtendedコミュニティであったりしていたのではなかろうか。しかしそれが軽薄化していき、そのあとにはインターネット/SNSというものができて現実世界のオルタナティブとしてのコミュニティの要素ができていった。しかし今のSNSはその特徴はあるにはあるが、悪い意味でのコミュニティの引力による分断化が進む中で、万人が独自のエコチェンバーの中でお互いを罵り合うことが多くなってきてしまっている。これでは拠り所とは正反対である。
⑨IoT商品の無印良品/AI-embedded なハード商品がほしい(△)
AI-embeddedなハードなものは、自分も今つかたりしているPlaudは今年の中ではヒット商品ではある。議事録というものを効率化してくれている。日本のスタートアップからはまだ残念ながらAI-embeddedなハードはまだおおくはでてきてはないが、今後よりそういった商品は出てくる気がしている。
IoTの無印っぽいコンセプトに近いのかもとは思えてきた。しかしうまくいっているかはわからない。ただもう少し店舗に行って買う理由づくり含めて、体験できるワクワクするような商品が増えればいいなとミーハーな消費者としては思う。アメトークの家電芸人ではないが、ガラパゴスと呼ばれていた昔の家電メーカーがいろんな面白い機能にチャレンジしたころが懐かしい。コスパなどではなく、人々が買う気になる理由ができる商品がふえることを期待している。
⑩Roll-up modelで様々な効率性をあげていける分野はまだあるのではないか(○)
GENDAの躍進は今年の大きなスタートアップ業界のニュースではあると思う。ロールアップのような戦略は、数年前から海外のスタートアップでThrasioのようなユニコーンなどがでていたものであるから注目は全員していた。
そこからしばらく経ち、GENDAのようなロールアップ型で上場していき株価も業績も良い推移を見せているものがでてきている。今後もファンドサイズなどの増加に対応できるほどの劇的な変化がなければ買収のためのVC調達などは増えてくる気配はある。
ここにはVCのファンドサイズの巨大化に伴い、Valuationが上がっていくなかでの、リターンをだすため/資本コストを乗り越えるためにはより指数関数的な成長が求められる。しかしそれを1事業で作ることは難しいため、Compoundというような複利を効かせていくための打ち手が求められる。それは事業ラインを増やすことも1つの答えであり、そのための買収,Roll-upというのは今後も増えるであろう。
⑪インディーズゲーム会社 from AI-scratched/Web3要素ありゲーム開発(○)
これは今年自分が投資はしてなかったが、当たった仮説なきもしている。パルワールドがこのブログを書いたあとにでてきており、驚異的な売上と驚異的な話題性をかっさらっていった。(もちろん法的な問題などはあるが)
steamの躍進などによってよりゲーム自体もDay0グローバルにいけることができるようになってきており、こういったところにはまだまだジャパンブランドも含めてレバレッジが効くような場所である気がしている。来年も注目したい分野である。
Steamの躍進:昔はゲームはどれかのハードデバイスで発売しないといけなかったが、スマフォンでアプリストアが開放され、また近年ではSteamが躍進しており、こういったインディーズゲーム会社にもグローバルへの道が開かれている。
⑫組織の力学をかえる仕組み/発明はないのか(✕)
特にこの領域は自分も特筆すべきことはあんまりないが、DAOというはやりワードが流行って廃れかけてはいるが、コンセプトや考え方は非常に自分は好きだ。そういった今後の社会において一社だけで働くという働き方は変化していくはずである。
そういったときに組織の力学を動かす仕組みを変えていく流れはより進んでいる。それはピアボーナスのような仕組みもそうだし、社内のなかで流通できるポイントをつくるような企業事例をいくつかみたことがあるがそういったものでもよいのかもしれない。
人材の流動性が増していくからこそ、社内へのエンゲージメント管理。副業中心のチームだからこそ自発的な運営をつくれるインセンティブ構造の発明。そういったものが今後より求められてくる時代にはより一層なるのではないか。
一方で、働き方の多様化含めて、組織というもののあり方、力学の動かし方というのはトップダウンの一律的な動き方ではなくなっていく流れは確かにあるし、一定度は不可逆ではある。ホラクラシーのような概念が徐々に浸透していっている流れも感じる。
ゆるやかな変化の時代
インターネットやスマートフォンなどのような大きな変化が2000年から2010年代ほどにはあった気がするが、そのぐらいのBigwaveや大きな変化はしばらくはない気がしている。VCとしては変化がないと利益がないので難しいが、過度に変化を期待しすぎてはならない。
一方で、確実に悪い意味においても国際情勢は変わりつつあるし、日常も劇的な変化はないが少しずつAIや、日常で利用するものは変化していく。そういったものを今後は捉えて投資をしていきたいし、この投資テーマは毎年VCになってからやっていたが、今後どのぐらいやっていこうかは考え中である。まあその年に着目していたものが知れるからゆるく続けていきたいが、コンテンツとしては面白くなくなっていく可能性もありうる。
毎年書いているので、その年の振り返りのためにもぜひ。ご笑覧ください。
流行っている本を積読していたが、期待以上に面白かった。
まさに自分もこの2-3ヶ月ほど特に仕事が忙しく読む暇がなかった、厳密には読む暇があっても本に手が伸びなかった。そういうのをハック的な方法論ではなく、出版・本の歴史から紐解き、今の現代社会における疲労について着目して書かれているどちらかというと哲学書に近い感覚の読了感があった。新書ってもう少しハックぽい本が多いなと思っていたので、すごく良い意味で裏切られた本。
ネオリベの精神性というものは特に自分も良い面も悪い面も非常に染まっているなと改めて読みながら感じた。特に20代は自己啓発的な役に立つものを読もうという感覚が強く、そういうノイズを排除していくことが進んでいったが、今は逆にそのノイズをいかに手に入れるかを個人的には意識している。
ネオリベ的なものは個性を尊重しながらもその個性で生き抜けというのを強いられてくる。それは実存の切り売りに繋がり、そういった文脈の中でしか生活ができなくなってくる。本の中にもあるが全身全霊で働くことは簡単だとある。しかし半身で働くことを提案を本を通してされており、違う文脈を取り入れるには仕事だけ!だと取り入れられない。結果本含めて自分の好きなこと、良い意味でノイズを取り入れることができる。その余裕を持つことができるのだということを書いてある。
自分も前述したが、仕事にどうしても全身全霊をかけてしまいがちだが20代でそれをやった結果この先にあるのはつまらない人間になってしまうかもという危機感があった。コスパ・タイパを突き詰めて行った先にあるのは何なのか?何もない可能性がある。そういった意味においても仕事をサボれっていうわけではないが、違う文脈を取り入れる余裕やノイズを入れれる余裕などは必要なように思える。特にVCという仕事は、全身全霊でやったから結果が出るわけでもない仕事。自分の芸の幅を広げていく意味においても最近はビジネス書を全く読まなくなったように、こういった違う文脈を自分の中に取り入れていく工夫をしなければなーとは考えている。
ただこれを書きながら気づいたが、それは全ては仕事・投資のためな感もあって自分はネオリベの精神にどっぷりだなあと改めて思う。それを脱することはできないかもしれないが、メタにそういう状態にある認知をした上で自分は幸せになるセンスがないということを捉えた上で自分も生き方を考えないといけないなっていうところまで考えさせられた本だった。おすすめ。